2024年12月5日、日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されてから一年が経過しました。これは、単に日本酒だけでなく、焼酎や泡盛を含む多岐にわたる日本の伝統的な醸造技術、それを支える人々の知恵、そして季節ごとの祭事や地域文化との結びつきが世界的に認められたことを意味します。
高まる国内外の認知度と期待
この一年で最も大きな変化は、国内および海外における認知度の劇的な向上です。メディアでの露出が増えたことはもちろん、特に欧米やアジアの富裕層・文化層の間で、単なるアルコール飲料としてではなく、「日本の歴史と風土が生んだ文化遺産」としての評価が定着し始めました。これにより、日本産酒類の輸出市場では、プレミアムライン、つまり高価格帯の商品の需要が高まる傾向が見られています。
一方で、現場の酒蔵には、労働環境の改善や後継者不足という依然として深刻な課題が残されています。無形文化遺産としての価値を将来にわたって維持するためには、これらの「技術の担い手」を確保・育成することが不可欠です。この一年間、各地の酒造組合や自治体は、蔵人の募集や研修制度の充実、さらには冬場に限られていた酒造りを四季醸造へ移行させるための技術導入など、働き方改革と技術継承の両輪での取り組みを加速させています。
「GI」との相乗効果:地域ブランド力の強化
「伝統的酒造り」の価値を具体的に市場に伝える上で、地理的表示(GI:Geographical Indication)制度の存在は欠かせません。GI制度は、特定の産地ならではの特性を持つ産品を保護し、その品質と評判を保証するものです。
ユネスコ無形文化遺産登録は、日本の酒造り全体に「文化的な権威」と「伝統というストーリー」を与えました。これに対し、GIは「具体的な品質基準」と「産地ごとの明確なアイデンティティ」を付与します。
例えば、「GI日本酒」や「GI山形」など、すでに登録されているGI表示が付いた日本酒は、無形文化遺産に裏打ちされた「伝統的技術で造られている」という大前提の上に、「この地域の特定の原料と風土が生み出した特徴を持つ」という二重のブランド価値を持つことになります。
この相乗効果により、特に地方の小規模ながらも個性的な酒蔵が、その地域のテロワール(風土)を表現した商品を、高付加価値なものとして国内外に訴求しやすくなりました。今後、GI登録を目指す地域も増加すると予想され、地域ごとの多様な酒造りの保護と発展に寄与するでしょう。
今後の課題と展望:持続可能な酒造りへ
登録一年という節目に立ち、日本の酒造業界が目指すのは「持続可能な酒造り」の実現です。
【技術のデジタル化とデータの活用】
伝統的な技術を若手に効率よく伝えるため、熟練蔵人の技術をデジタルデータとして記録し、温度管理などにAIを導入する動きが今後さらに広がることが予想されます。
【環境への配慮】
持続可能性の観点から、環境負荷の低い米作りへの回帰や、再生可能エネルギーの導入、水の利用効率改善など、環境と調和した酒造りへの取り組みが、国内外の消費者にとって重要な選択基準となるでしょう。
無形文化遺産登録は、日本の酒造業界が、過去の技術をただ守るだけでなく、それを現代の課題解決と融合させ、未来に進化させていくための大きな契機となりました。この登録を追い風に、日本酒・焼酎・泡盛が、世界の文化遺産として、より広く、より深く愛される存在となることが期待されます。

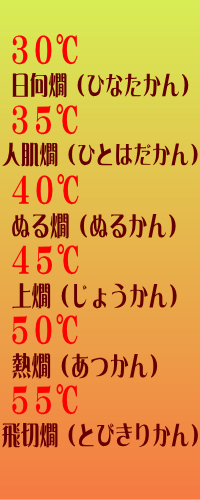 まず注目されるのは、温度上昇による揮発性成分の変化です。日本酒にはリンゴ酸、コハク酸、乳酸などの有機酸や、酢酸イソアミル、カプロン酸エチルといった香気成分が含まれています。これらは温度が上がると揮発しやすくなり、香りの立ち方に大きな影響を与えます。特に酢酸イソアミルなどの「吟醸香」と呼ばれるフルーティーな成分は低温で感じやすい一方、燗をつけることでアルコール由来の香りや米のうま味を想起させる成分が前面に出やすくなります。そのため、吟醸酒よりも純米酒や本醸造酒が燗酒と相性がよいとされる理由が、科学的にも裏付けられつつあります。
まず注目されるのは、温度上昇による揮発性成分の変化です。日本酒にはリンゴ酸、コハク酸、乳酸などの有機酸や、酢酸イソアミル、カプロン酸エチルといった香気成分が含まれています。これらは温度が上がると揮発しやすくなり、香りの立ち方に大きな影響を与えます。特に酢酸イソアミルなどの「吟醸香」と呼ばれるフルーティーな成分は低温で感じやすい一方、燗をつけることでアルコール由来の香りや米のうま味を想起させる成分が前面に出やすくなります。そのため、吟醸酒よりも純米酒や本醸造酒が燗酒と相性がよいとされる理由が、科学的にも裏付けられつつあります。


